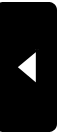2016/07/28
黒姫山に祀られているのは「黒姫弁財天」であるというのがはじまりで、確かに信濃町雲龍寺に里宮があった。
しかし、この神仏の性格・由来がわからない。
弁財天というのは、いろいろな女神の本地となる。
【本地垂迹説】————
本地である仏・菩薩が,救済する衆生の能力に合わせた形態をとってこの世に出現してくるという説。日本では神道の諸神を垂迹と考える神仏習合思想が鎌倉時代に整備されたが,その発生は平安以前にさかのぼる。垂迹である神と,本地である仏・菩薩との対応は必ずしも一定していない。
————————大辞林
日本三大弁天と言われる神社では
・滋賀県竹生島は市杵島比売命(ただし産土神は浅井比売命)
・神奈川県江ノ島は宗像三女神(多紀理比賣命、市寸島比賣命、田寸津比賣命)
・広島県厳島神社も宗像三女神(市杵島姫命、田心姫命、湍津姫)
と、いずれも宗像系の海の神を祀っている。
ただし、飛鳥時代に役行者が開創したと伝えられ、三大弁天に入れることもある、奈良県吉野・天河神社の「天河弁財天」は、はじめから弁財天であり、神仏分離によって市杵島姫命となったが、瀬織津姫の説もある。
黒姫弁財天に関しては、いまのところ記録はみつからないので、少し視点を離してみる。
---------------------------------
長野では唯一の黒姫山だが、新潟では、頚城山塊をとりまく三つの黒姫山の一つとして認識されているという。
信州黒姫山と青梅黒姫山、刈羽黒姫山の三つである。
北信と上越地方は、武田上杉の争いの舞台となり領域が有為転変したように、もともと地理的文化的な近さがあり、特に善光寺平以北は、上杉氏の関与が深い。
そんな距離感にある、同じ名前の山である。
こちらに無いなら、向こうを調べればヒントがあるかもしれない、と思って調べてみる。
青梅黒姫山(糸魚川市) 1,222m 三百名山
山頂は黒姫権現を祀る。
「黒姫権現とは沼河姫(ヌナカワヒメ)である」という説と、
「奴奈川姫の母が黒姫命である」という説がある。
刈羽黒姫山(柏崎市) 889.5m
山頂近くに鵜川神社を祀る。
「鵜川神社」祭神は美都波能売神(ミヅハノメカミ)と黒姫大明神。
「黒姫大明神は奴奈川姫(ヌナカワヒメ)命である」
??
新潟の黒姫山に祀られているのは奴奈川姫。
(表記が多様だが、ここでは奴奈川姫で統一)
信州黒姫山にはいない「黒姫権現」や「黒姫大明神」が祀られ、それは奴奈川姫という。
奴奈川姫とはなにか。
糸魚川市ホームページ
「奴奈川姫の伝説」
奴奈川姫は『古事記』に登場する「高志国」の姫であり、出雲から来た大国主の妃となった。諏訪神社のご祭神である建御名方神(タケミナカタ)を生んだともいわれる。
国譲りの神である大国主の一族が出雲から移動し、新潟の土豪と結びつき、新たな集団を作り内陸へ糸魚川をさかのぼり、守屋の一族と諏訪信仰を生んだ、古代の人の流れの物語の一端をしのばせる。
黒姫山と奴奈川姫の伝説が結びつくのなら、思っているよりも古い由来となる。
奴奈川姫と黒姫のつながりを探して、新潟へ行く。
---------------------------------
『延喜式』(平安中期編纂)にある「奴奈川神社」が、最も古い奴奈川姫を祀る神社の記録だが、現在地は明確ではない。
候補の一つが、糸魚川市の能生白山神社である。

能生白山神社はかつて奴奈川神社と称し、この一帯の産土神であり、もとは「高志峰」にあった。
「高志峰」は、いまの「権現岳」であり、奥社が祀られているという。
奈良時代に加賀白山神社を開いた泰澄法師が白山信仰を布教し、白山神社となった。
(ただし祭神は大国主と奴奈川姫と伊奘諾命で、白山比咩神=菊理媛を祀っていない)
では、奴奈川姫を初期に祀ったのは、権現岳の奥社だろうか。
ということで、権現岳に登ります。

能生白山神社、補修工事中でした。
茅葺の拝殿は江戸時代の見事な建物。
しかし、この神仏の性格・由来がわからない。
弁財天というのは、いろいろな女神の本地となる。
【本地垂迹説】————
本地である仏・菩薩が,救済する衆生の能力に合わせた形態をとってこの世に出現してくるという説。日本では神道の諸神を垂迹と考える神仏習合思想が鎌倉時代に整備されたが,その発生は平安以前にさかのぼる。垂迹である神と,本地である仏・菩薩との対応は必ずしも一定していない。
————————大辞林
日本三大弁天と言われる神社では
・滋賀県竹生島は市杵島比売命(ただし産土神は浅井比売命)
・神奈川県江ノ島は宗像三女神(多紀理比賣命、市寸島比賣命、田寸津比賣命)
・広島県厳島神社も宗像三女神(市杵島姫命、田心姫命、湍津姫)
と、いずれも宗像系の海の神を祀っている。
ただし、飛鳥時代に役行者が開創したと伝えられ、三大弁天に入れることもある、奈良県吉野・天河神社の「天河弁財天」は、はじめから弁財天であり、神仏分離によって市杵島姫命となったが、瀬織津姫の説もある。
黒姫弁財天に関しては、いまのところ記録はみつからないので、少し視点を離してみる。
---------------------------------
長野では唯一の黒姫山だが、新潟では、頚城山塊をとりまく三つの黒姫山の一つとして認識されているという。
信州黒姫山と青梅黒姫山、刈羽黒姫山の三つである。
北信と上越地方は、武田上杉の争いの舞台となり領域が有為転変したように、もともと地理的文化的な近さがあり、特に善光寺平以北は、上杉氏の関与が深い。
そんな距離感にある、同じ名前の山である。
こちらに無いなら、向こうを調べればヒントがあるかもしれない、と思って調べてみる。
青梅黒姫山(糸魚川市) 1,222m 三百名山
山頂は黒姫権現を祀る。
「黒姫権現とは沼河姫(ヌナカワヒメ)である」という説と、
「奴奈川姫の母が黒姫命である」という説がある。
刈羽黒姫山(柏崎市) 889.5m
山頂近くに鵜川神社を祀る。
「鵜川神社」祭神は美都波能売神(ミヅハノメカミ)と黒姫大明神。
「黒姫大明神は奴奈川姫(ヌナカワヒメ)命である」
??
新潟の黒姫山に祀られているのは奴奈川姫。
(表記が多様だが、ここでは奴奈川姫で統一)
信州黒姫山にはいない「黒姫権現」や「黒姫大明神」が祀られ、それは奴奈川姫という。
奴奈川姫とはなにか。
糸魚川市ホームページ
「奴奈川姫の伝説」
奴奈川姫は『古事記』に登場する「高志国」の姫であり、出雲から来た大国主の妃となった。諏訪神社のご祭神である建御名方神(タケミナカタ)を生んだともいわれる。
国譲りの神である大国主の一族が出雲から移動し、新潟の土豪と結びつき、新たな集団を作り内陸へ糸魚川をさかのぼり、守屋の一族と諏訪信仰を生んだ、古代の人の流れの物語の一端をしのばせる。
黒姫山と奴奈川姫の伝説が結びつくのなら、思っているよりも古い由来となる。
奴奈川姫と黒姫のつながりを探して、新潟へ行く。
---------------------------------
『延喜式』(平安中期編纂)にある「奴奈川神社」が、最も古い奴奈川姫を祀る神社の記録だが、現在地は明確ではない。
候補の一つが、糸魚川市の能生白山神社である。

能生白山神社はかつて奴奈川神社と称し、この一帯の産土神であり、もとは「高志峰」にあった。
「高志峰」は、いまの「権現岳」であり、奥社が祀られているという。
奈良時代に加賀白山神社を開いた泰澄法師が白山信仰を布教し、白山神社となった。
(ただし祭神は大国主と奴奈川姫と伊奘諾命で、白山比咩神=菊理媛を祀っていない)
では、奴奈川姫を初期に祀ったのは、権現岳の奥社だろうか。
ということで、権現岳に登ります。

能生白山神社、補修工事中でした。
茅葺の拝殿は江戸時代の見事な建物。
2016/07/17
黒姫弁財天を探しながら、気になる民話に出会った。
信濃町の「ポックリ地蔵」。
戸隠と信濃町の関わりが偲ばれる民話である。
あらすじは
「仁之倉によく働くじいさまがいて、戸隠へ米や蕎麦を運び、黒姫山の草刈りをして暮らしていた。
ある日、黒姫山麓の笹原で地蔵の石仏を見つけ、ノゾキ井戸という畳一枚ほどの泉のほとりに移した。
通るたびにお参りし、日々よく働いた。
20年よく働き、85歳でお地蔵さまをお連れし、90まで働き、ぽっくりと亡くなった。
じいさまにあやかって、ポックリ地蔵と呼び、みなお参りするようになった」
というお話。
全文は、良いアーカイブであるJAながの「ふるさとの民話」で、倉石画伯の挿絵とともにどうぞ。
ふるさとの民話「ポックリ地蔵」
http://www.ja-nagano.iijan.or.jp/legend/2011/03/92.php
戸隠から仁之倉を通り、北国街道へつながる道は「越後道」とよばれ、信濃町側では「戸隠山道」という。
戸隠からは豊岡、折橋で鬼無里からの道と合流し、善光寺へ、また峠を越え小市から篠ノ井へと続く巡礼と物流の道である。
折橋は物資の参集地として賑わい、信濃町を朝発った荷馬がちょうど昼に着くので、農家は昼食の目安にしたという。(『柵村誌』より)
そんな往来が、人の生活として感じられる民話だと思う。
仁之倉、黒姫山、戸隠の他に、場所を示すものとして
じいさまがお地蔵さま見つけた山奥の笹っ原、
街道すじの「ノゾキ井戸」という泉、
が記録されている。
------------------------------------------
まず、仁之倉「ポックリ地蔵」をお参りしに行く。
小林一茶生母の家にほど近い、旧道筋に道標があり、民家の庭先に安置されている。
お参りして、失礼ながらとよく見て驚いたことに
お地蔵さまではない!
「厄除観音」!
「駒形石 厄除観音 文化元年 大聖院 建立」
と読み取れる。
大聖院は、江戸初〜中期創立、明治7年廃寺となった仁之倉の寺である。
山号は「飯縄山大聖院」であったと『長野県町村誌』にある。
町村誌には、大聖院を含め、明治初期に廃寺となった3つの寺が記録され、廃仏毀釈により整理されたと推測される。
駒形石という岩が近くにあったのだろうか?
石仏の形態がどうであれ
・仁之倉に元気で信心深いじいさまがいて、大事に祀っていた石仏があった。
・石仏はじいさまにあやかって「ポックリ地蔵」と呼ばれた。
という民話の筋は変わらない。
また、家にお連れしようと思ったけど、やはりそのままにしておいて、今もまだ山中の泉のそばにお地蔵さまがある、という景色も 思い描ける。
-----------------------------------------------
さて、「ノゾキ井戸」である。
街道筋の「畳1枚ほどの泉」といって連想するのは、県道沿いにある「一杯清水」である。
井戸は井戸であって、泉の名前にしっくりこないが、少なくとも「ノゾキ」というのだから、高いところにあって下を見おろす地形だろうが、県道整備によって当時の地形はわからなくなっている。
「一杯清水」も地形図や「山と高原地図」に記載がありながら、看板等はないので、県道を通るたびに気になっていた。
地図をたよりに探してみると、草薮のなかに確かにそれらしき泉があった。
山道の貴重な水場であっただろう小さな泉で、そばに馬頭観音が二つ。
一つには「右 やまみち 左 とがくし」という明治29年のもの(左)。

信濃町の「ポックリ地蔵」。
戸隠と信濃町の関わりが偲ばれる民話である。
あらすじは
「仁之倉によく働くじいさまがいて、戸隠へ米や蕎麦を運び、黒姫山の草刈りをして暮らしていた。
ある日、黒姫山麓の笹原で地蔵の石仏を見つけ、ノゾキ井戸という畳一枚ほどの泉のほとりに移した。
通るたびにお参りし、日々よく働いた。
20年よく働き、85歳でお地蔵さまをお連れし、90まで働き、ぽっくりと亡くなった。
じいさまにあやかって、ポックリ地蔵と呼び、みなお参りするようになった」
というお話。
全文は、良いアーカイブであるJAながの「ふるさとの民話」で、倉石画伯の挿絵とともにどうぞ。
ふるさとの民話「ポックリ地蔵」
http://www.ja-nagano.iijan.or.jp/legend/2011/03/92.php
戸隠から仁之倉を通り、北国街道へつながる道は「越後道」とよばれ、信濃町側では「戸隠山道」という。
戸隠からは豊岡、折橋で鬼無里からの道と合流し、善光寺へ、また峠を越え小市から篠ノ井へと続く巡礼と物流の道である。
折橋は物資の参集地として賑わい、信濃町を朝発った荷馬がちょうど昼に着くので、農家は昼食の目安にしたという。(『柵村誌』より)
そんな往来が、人の生活として感じられる民話だと思う。
仁之倉、黒姫山、戸隠の他に、場所を示すものとして
じいさまがお地蔵さま見つけた山奥の笹っ原、
街道すじの「ノゾキ井戸」という泉、
が記録されている。
------------------------------------------
まず、仁之倉「ポックリ地蔵」をお参りしに行く。
小林一茶生母の家にほど近い、旧道筋に道標があり、民家の庭先に安置されている。
お参りして、失礼ながらとよく見て驚いたことに
お地蔵さまではない!

「厄除観音」!
「駒形石 厄除観音 文化元年 大聖院 建立」
と読み取れる。
大聖院は、江戸初〜中期創立、明治7年廃寺となった仁之倉の寺である。
山号は「飯縄山大聖院」であったと『長野県町村誌』にある。
町村誌には、大聖院を含め、明治初期に廃寺となった3つの寺が記録され、廃仏毀釈により整理されたと推測される。
駒形石という岩が近くにあったのだろうか?
石仏の形態がどうであれ
・仁之倉に元気で信心深いじいさまがいて、大事に祀っていた石仏があった。
・石仏はじいさまにあやかって「ポックリ地蔵」と呼ばれた。
という民話の筋は変わらない。
また、家にお連れしようと思ったけど、やはりそのままにしておいて、今もまだ山中の泉のそばにお地蔵さまがある、という景色も 思い描ける。
-----------------------------------------------
さて、「ノゾキ井戸」である。
街道筋の「畳1枚ほどの泉」といって連想するのは、県道沿いにある「一杯清水」である。
井戸は井戸であって、泉の名前にしっくりこないが、少なくとも「ノゾキ」というのだから、高いところにあって下を見おろす地形だろうが、県道整備によって当時の地形はわからなくなっている。
「一杯清水」も地形図や「山と高原地図」に記載がありながら、看板等はないので、県道を通るたびに気になっていた。
地図をたよりに探してみると、草薮のなかに確かにそれらしき泉があった。
山道の貴重な水場であっただろう小さな泉で、そばに馬頭観音が二つ。
一つには「右 やまみち 左 とがくし」という明治29年のもの(左)。

戸隠イースタンキャンプ場の前にも
「右 やまみち 左 えちご道」
とかかれた道標がある。

いろいろみていくと、左右の行き先を示す案内の文字は、旧道の分岐点に置かれる道標や石仏に刻まれることが多い。
一杯清水も水場なので、「ひと息ついたあとに方向を見失う道迷い」を防ぐ目的で置かれたのかもしれない。
また、仁之倉の知人に「一杯清水」について
「一杯清水は、かつて茶屋があって、泉のほとりには柳の木があった。
県道をバスが通っていた頃は、「一杯清水」というバス停があった」
という話を聞いた。
ノゾキ井戸にはたどり着けないが、山道の往時と、県道のなりたちが偲ばれる。
--------------------------------
余談だが、個人的に気になるのは
「新しい年が来るたび、年を一つずつ減らしていくように、体がよく動いた」
というくだりである。
妙に具体的なじいさまの年齢は
65歳 お地蔵さまを見つける。以後20年よく働く。
85歳 思い立ちお地蔵さまをお連れする
90歳 ぽっくりと亡くなる。
すでに物語のはじめで65歳と、当時にしては高齢なのに、毎年減っていくと、20年働いて45歳並み?
「よく働くことができてよかった」というのは、「ラクして幸せになった」という「めでたし」とは別の功徳である。
逆浦島太郎というか、「ノゾキ井戸」という異界の入り口から何かを得て、若返りの幸を得る異界訪問譚としてみると、ちょっと面白いが、また別の物語になりそう。
「右 やまみち 左 えちご道」
とかかれた道標がある。

いろいろみていくと、左右の行き先を示す案内の文字は、旧道の分岐点に置かれる道標や石仏に刻まれることが多い。
一杯清水も水場なので、「ひと息ついたあとに方向を見失う道迷い」を防ぐ目的で置かれたのかもしれない。
また、仁之倉の知人に「一杯清水」について
「一杯清水は、かつて茶屋があって、泉のほとりには柳の木があった。
県道をバスが通っていた頃は、「一杯清水」というバス停があった」
という話を聞いた。
ノゾキ井戸にはたどり着けないが、山道の往時と、県道のなりたちが偲ばれる。
--------------------------------
余談だが、個人的に気になるのは
「新しい年が来るたび、年を一つずつ減らしていくように、体がよく動いた」
というくだりである。
妙に具体的なじいさまの年齢は
65歳 お地蔵さまを見つける。以後20年よく働く。
85歳 思い立ちお地蔵さまをお連れする
90歳 ぽっくりと亡くなる。
すでに物語のはじめで65歳と、当時にしては高齢なのに、毎年減っていくと、20年働いて45歳並み?
「よく働くことができてよかった」というのは、「ラクして幸せになった」という「めでたし」とは別の功徳である。
逆浦島太郎というか、「ノゾキ井戸」という異界の入り口から何かを得て、若返りの幸を得る異界訪問譚としてみると、ちょっと面白いが、また別の物語になりそう。
2016/07/13
さて「ゴウロ」である。
『長野県町村誌』に「黒姫弁財天の里堂は字ゴウロにあり」と記録されている、里堂を探しに行く。
ゴウロとは、芋井の狢郷路山(むじなごうろやま)や、木島平の朝日ゴウロ(古墳)のように、岩っぽい場所を指すことが多い名前である。
しかし、普通の地図で信濃町を見ても、地名としては見あたらない。
自分の住んでいない土地の「字」名を探るのは、けっこう難しい。
地図を見てもわからなかったが、雲龍寺さんから場所を教えてもらうことができた。
黒姫山の表登山道(東登山道)の入り口にある、町民の森近くに「ゴウロ」があるとのことだった。
(教えてもらわなければ分からなかった!)
通りかかっても意識しにくいところに、きちんと看板が立っている。
「黒姫山別当職 寳林禅寺 雲龍寺中之宮跡 是より250m先」と書かれた看板が、ゴウロの入り口とのことだった。

黒姫山の裾野の森の中だが、かつては採石場であり、材木を育てる場であったのだろう。
よく見ると灌木の下に、ところどころ巨岩が眠っている。
黒姫山の稜線が、木々の合間からはっきりと見える。
山を拝める場所だ。
たしかにここは、古い信仰の跡であると感じられた。
-------------------------------
つぎは、はじめに黒姫弁財天が祀られたという「五輪堂」を探す。
『町村誌』に「恵心僧都が黒姫山に登って黒姫弁財天の像を作り、五輪堂にある宝教寺に祀った」とある五輪堂である。
(このへんは別説もあるので、要検証)
ネットで検索すると、『柏原町区史』に五輪堂(遺跡)に関する記述があることがわかった。
また、踏切の名称に「五輪堂」があることから、大体の場所がつかめる。
「五輪堂遺跡」は、縄文時代と平安期の出土があり、古くから人の住んでいた場所らしい。
五輪堂踏切を起点に、黒姫山の方へ道を辿ると、古い道標に出会う。
「右 戸隠山道 左 さくば道」
と描かれている。
古道の交差する道しるべである。


(ちなみに五輪堂踏切は、1987年に「球電」と言われる発光現象が撮影されたことでも有名らしく、検索の過程で不思議な画像にも出会った)
『長野県町村誌』に「黒姫弁財天の里堂は字ゴウロにあり」と記録されている、里堂を探しに行く。
ゴウロとは、芋井の狢郷路山(むじなごうろやま)や、木島平の朝日ゴウロ(古墳)のように、岩っぽい場所を指すことが多い名前である。
しかし、普通の地図で信濃町を見ても、地名としては見あたらない。
自分の住んでいない土地の「字」名を探るのは、けっこう難しい。
地図を見てもわからなかったが、雲龍寺さんから場所を教えてもらうことができた。
黒姫山の表登山道(東登山道)の入り口にある、町民の森近くに「ゴウロ」があるとのことだった。
(教えてもらわなければ分からなかった!)
通りかかっても意識しにくいところに、きちんと看板が立っている。
「黒姫山別当職 寳林禅寺 雲龍寺中之宮跡 是より250m先」と書かれた看板が、ゴウロの入り口とのことだった。

轍跡のある草道を入り、水路を渡っていくと、突如開けた場所に出る。
小高い丘の上に、石祠が3基。
ゴウロ、中の宮である。

杉と雑木に囲まれ、水音が響く、西陽の明るい窪地。
石祠は真東を向いて立っている。
文字らしきものは読み取れないので、黒姫弁財天かどうかは分からない。
左の祠は半分になっている。

よく見ると、緑に覆われた丘は、大きな岩である。
石祠と同じ、白い斑のある岩。
ゴウロは岩を産する地名であり、鉄道の敷石を採掘したということも雲龍寺さんは教えてくれた。
小高い丘の上に、石祠が3基。
ゴウロ、中の宮である。

杉と雑木に囲まれ、水音が響く、西陽の明るい窪地。
石祠は真東を向いて立っている。
文字らしきものは読み取れないので、黒姫弁財天かどうかは分からない。
左の祠は半分になっている。

よく見ると、緑に覆われた丘は、大きな岩である。
石祠と同じ、白い斑のある岩。
ゴウロは岩を産する地名であり、鉄道の敷石を採掘したということも雲龍寺さんは教えてくれた。
黒姫山の裾野の森の中だが、かつては採石場であり、材木を育てる場であったのだろう。
よく見ると灌木の下に、ところどころ巨岩が眠っている。
黒姫山の稜線が、木々の合間からはっきりと見える。
山を拝める場所だ。
たしかにここは、古い信仰の跡であると感じられた。
-------------------------------
つぎは、はじめに黒姫弁財天が祀られたという「五輪堂」を探す。
『町村誌』に「恵心僧都が黒姫山に登って黒姫弁財天の像を作り、五輪堂にある宝教寺に祀った」とある五輪堂である。
(このへんは別説もあるので、要検証)
ネットで検索すると、『柏原町区史』に五輪堂(遺跡)に関する記述があることがわかった。
また、踏切の名称に「五輪堂」があることから、大体の場所がつかめる。
「五輪堂遺跡」は、縄文時代と平安期の出土があり、古くから人の住んでいた場所らしい。
五輪堂踏切を起点に、黒姫山の方へ道を辿ると、古い道標に出会う。
「右 戸隠山道 左 さくば道」
と描かれている。
古道の交差する道しるべである。

『柏原町区史』昭和63年発行「戸隠山道(P.242)」には
「善光寺方面から登る表参道とは別に、柏原からは戸隠山に通じる裏道があった。宿場(柏原宿)の中心部から西側に分岐して仁之倉を経て、湯ノ入川沿いから黒姫山・飯縄山の山峡を西上して、大橋・念仏池・越水ケ原、そして中社・奥社へ通じる」
とある。
そのまま東へ行くと北国街道へつながる、往還の交差する地点である。
「善光寺方面から登る表参道とは別に、柏原からは戸隠山に通じる裏道があった。宿場(柏原宿)の中心部から西側に分岐して仁之倉を経て、湯ノ入川沿いから黒姫山・飯縄山の山峡を西上して、大橋・念仏池・越水ケ原、そして中社・奥社へ通じる」
とある。
そのまま東へ行くと北国街道へつながる、往還の交差する地点である。
詳細は不明ながら、この戸隠山道の起点に「五輪堂」があり、そこを「大昔は黒姫弁財天が祀られていた」と明治の人々が認識していたという事実がある。
位置的に、人が住みやすい平らで水がある耕地の高台が、初期の五輪堂であろうことは、地形を見れば推測できる。

黒姫山信仰には、黒姫山の位置と往来の道と水の流れ、戸隠とのつながりもあるのではないかと思わせる、わずかな記録と古い道標が、さらなる探索を誘う。
位置的に、人が住みやすい平らで水がある耕地の高台が、初期の五輪堂であろうことは、地形を見れば推測できる。

黒姫山信仰には、黒姫山の位置と往来の道と水の流れ、戸隠とのつながりもあるのではないかと思わせる、わずかな記録と古い道標が、さらなる探索を誘う。
それぞれの位置図。
紫の線は、古い街道の一部。

(ちなみに五輪堂踏切は、1987年に「球電」と言われる発光現象が撮影されたことでも有名らしく、検索の過程で不思議な画像にも出会った)
2016/07/04
ひさしぶりに趣味の記事。
---------------------------------------------------
信濃、黒姫山山頂には、石祠がある。
石版には「大毘沙門天、黒姫弁財天、七ツ池龍王」と刻まれている。

黒姫山は標高2,053m、おだやかな山容と登りやすい登山道、素晴らしい展望があり、年に一度は登る山だが、今年あらためて、この石版が気になった。
「七ツ池龍王」は「黒姫伝説」を連想させるが、黒姫山に龍王がいるという説があっただろうか?
「毘沙門天」は上杉氏を連想させる。
そして「黒姫弁財天」である。
三者のつながりが見えにくい並びに、黒姫山信仰とはどういうものであるか、全く知識がないことに気がついた。
戸隠には、江戸初期といわれる「九頭龍弁財天」の美しい像があり、九頭龍神(九頭龍社)と弁財天の信仰が知られる。
しかし「黒姫弁財天」とはなにものだろうか。
戸隠山には戸隠神社、天手力男命をはじめとする天の岩戸開きの神々と地主神の九頭龍神への信仰。
妙高山には関山神社、関山権現、阿弥陀三尊、火祭り。
飯縄山には飯縄神社、飯縄大権現。
山には奥社、里には里宮。
では黒姫山の山頂が奥社としたら、里宮はどこに?
黒姫弁財天を探しに行く。
インターネットで検索しても、意外に関連する記述はでてこない。
石祠がそれなりに古いので、少し古い資料に当たってみる。
こういうときに便利なのが、
『長野縣町村誌』昭和11年刊行。
いわゆる皇国地誌で、明治15年に長野県令あて報告された当時の地勢が記録されている。
そこにはしっかり「黒姫弁財天」の項が設けられている。
信濃町において「黒姫山を祀っているのは雲龍寺さん」というのは常識らしい。
黒姫山信仰、戸隠と妙高の間にある美しい山への信仰のあとをたどりたくなった。
次はゴウロへ。
---------------------------------------------------
信濃、黒姫山山頂には、石祠がある。
石版には「大毘沙門天、黒姫弁財天、七ツ池龍王」と刻まれている。

黒姫山は標高2,053m、おだやかな山容と登りやすい登山道、素晴らしい展望があり、年に一度は登る山だが、今年あらためて、この石版が気になった。
「七ツ池龍王」は「黒姫伝説」を連想させるが、黒姫山に龍王がいるという説があっただろうか?
「毘沙門天」は上杉氏を連想させる。
そして「黒姫弁財天」である。
三者のつながりが見えにくい並びに、黒姫山信仰とはどういうものであるか、全く知識がないことに気がついた。
戸隠には、江戸初期といわれる「九頭龍弁財天」の美しい像があり、九頭龍神(九頭龍社)と弁財天の信仰が知られる。
しかし「黒姫弁財天」とはなにものだろうか。
戸隠山には戸隠神社、天手力男命をはじめとする天の岩戸開きの神々と地主神の九頭龍神への信仰。
妙高山には関山神社、関山権現、阿弥陀三尊、火祭り。
飯縄山には飯縄神社、飯縄大権現。
山には奥社、里には里宮。
では黒姫山の山頂が奥社としたら、里宮はどこに?
黒姫弁財天を探しに行く。
インターネットで検索しても、意外に関連する記述はでてこない。
石祠がそれなりに古いので、少し古い資料に当たってみる。
こういうときに便利なのが、
『長野縣町村誌』昭和11年刊行。
いわゆる皇国地誌で、明治15年に長野県令あて報告された当時の地勢が記録されている。
そこにはしっかり「黒姫弁財天」の項が設けられている。

『長野縣町村史』昭和11年発行 P.524)
---------------------------------------------------
(以下引用、新字体にあらためている)
「石祠黒姫山の嶺上にあり。里俗伝に、大宝2年役の小角この山に登り、七ツ池に至り弁財天を拝す。寛仁4年9月、恵心僧都この山に登りて誓願し、黒姫弁財天の像を刻み、仏体となす。(相模国江ノ島弁財天と同体なりという)
本村宝教寺(字五輪堂にあり)右、弁財天の別当となる。
数世を経て、元和元年、下水内郡永江村天正寺住僧明室、宝教寺へ転住す。
その弟子、僧 潭深雲龍継ぐ。
延宝2年6月、この寺を字赤渋へ移し、黒姫山雲龍寺と改称し、旧のごとく黒姫弁財天の別当たり。宝永3年領主永井伊賀守深く信仰し、大般若経600巻を寄付す。
のち宝暦6年、永井氏、その臣 阿部甚七なるものを使わして、字ゴウロにおいて里堂を建設し、杉苗千本を植えしむ。(以下略)」
---------------------------------------------------
寺社のなりたちで、有名な「役の小角(えんのおづぬ、飛鳥〜奈良時代、修験道の祖といわれる)」や「恵心僧都(えしんそうず、源信、平安中期の天台宗の僧、『往生要集』)」を出す場合、ほとんど名義借りであるとはよくいわれる。
丁寧に年号を記しつつ、大宝元(701)年に没したとされる役の小角の来訪を、翌大宝2年としていたり、寛仁元(1017)年に没したとされる恵心僧都の来訪を、寛仁4年としたりという点で、ほぼニアミスのため、日本史の大要が把握されている江戸中後期頃の認識と思われる。
または伝説を明治初期の役人が記述する際、それらしく仕上げたか。
---------------------------------------------------
(以下引用、新字体にあらためている)
「石祠黒姫山の嶺上にあり。里俗伝に、大宝2年役の小角この山に登り、七ツ池に至り弁財天を拝す。寛仁4年9月、恵心僧都この山に登りて誓願し、黒姫弁財天の像を刻み、仏体となす。(相模国江ノ島弁財天と同体なりという)
本村宝教寺(字五輪堂にあり)右、弁財天の別当となる。
数世を経て、元和元年、下水内郡永江村天正寺住僧明室、宝教寺へ転住す。
その弟子、僧 潭深雲龍継ぐ。
延宝2年6月、この寺を字赤渋へ移し、黒姫山雲龍寺と改称し、旧のごとく黒姫弁財天の別当たり。宝永3年領主永井伊賀守深く信仰し、大般若経600巻を寄付す。
のち宝暦6年、永井氏、その臣 阿部甚七なるものを使わして、字ゴウロにおいて里堂を建設し、杉苗千本を植えしむ。(以下略)」
---------------------------------------------------
寺社のなりたちで、有名な「役の小角(えんのおづぬ、飛鳥〜奈良時代、修験道の祖といわれる)」や「恵心僧都(えしんそうず、源信、平安中期の天台宗の僧、『往生要集』)」を出す場合、ほとんど名義借りであるとはよくいわれる。
丁寧に年号を記しつつ、大宝元(701)年に没したとされる役の小角の来訪を、翌大宝2年としていたり、寛仁元(1017)年に没したとされる恵心僧都の来訪を、寛仁4年としたりという点で、ほぼニアミスのため、日本史の大要が把握されている江戸中後期頃の認識と思われる。
または伝説を明治初期の役人が記述する際、それらしく仕上げたか。
年号のずれは、当時の知識によるものか、意図的なものかは不明。
具体的になるのは、下水内郡永江村からのつながりである。
永江村は、飯山藩に属し、今の中野市豊田にある。
飯山藩における位置づけ、黒姫伝説に語られる中野高梨氏(黒姫は高梨氏の姫とする伝説が多い)とのつながりが、この辺の由来だろうか。
具体的になるのは、下水内郡永江村からのつながりである。
永江村は、飯山藩に属し、今の中野市豊田にある。
飯山藩における位置づけ、黒姫伝説に語られる中野高梨氏(黒姫は高梨氏の姫とする伝説が多い)とのつながりが、この辺の由来だろうか。
地名と現状から、根拠がありそうだと思われるのは以下の点。
・まず、五輪堂という場所に、黒姫弁財天が祀られた。
・永江村から来た僧が、これを継いだ。
・その弟子の僧「雲龍」が、赤渋に移転し、黒姫山雲龍寺と改称した。
・字ゴウロに里堂を建てた。
宝永元年(1704)に、播磨赤穂藩から移封された永井直敬(江戸時代の譜代大名、1664〜1711、1706〜1711飯山藩主)が、着任後に大般若経の類を寄付したというのは、ありそうである。寺に伝えられているかもしれない。
だが、永井氏は宝永8(1711)年に武蔵岩槻藩へ移封されるので、宝暦年間(1756)の記録は「本多氏(飯山藩主1717〜廃藩置県まで)」であろうか。
が、享保2(1717)年以降この地域は幕府領となるため、あいまいとなる。
阿部甚七なる人物は、いたかもしれない。
ただ、このころ杉千本を植えることができる所領を、雲龍寺が保有して、それが字ゴウロのあたりであり、そこへ里堂を建てた、ということは具体的な事実と思われる。
---------------------------------------------------
・永江村から来た僧が、これを継いだ。
・その弟子の僧「雲龍」が、赤渋に移転し、黒姫山雲龍寺と改称した。
・字ゴウロに里堂を建てた。
宝永元年(1704)に、播磨赤穂藩から移封された永井直敬(江戸時代の譜代大名、1664〜1711、1706〜1711飯山藩主)が、着任後に大般若経の類を寄付したというのは、ありそうである。寺に伝えられているかもしれない。
だが、永井氏は宝永8(1711)年に武蔵岩槻藩へ移封されるので、宝暦年間(1756)の記録は「本多氏(飯山藩主1717〜廃藩置県まで)」であろうか。
が、享保2(1717)年以降この地域は幕府領となるため、あいまいとなる。
阿部甚七なる人物は、いたかもしれない。
ただ、このころ杉千本を植えることができる所領を、雲龍寺が保有して、それが字ゴウロのあたりであり、そこへ里堂を建てた、ということは具体的な事実と思われる。
---------------------------------------------------
信濃町柏原赤渋 雲龍寺を訪問。
寺の一角には「弁財尊天」の祠があり、近年新しくなったという
「黒姫里之宮
黒姫山に
上之宮
寺の一角には「弁財尊天」の祠があり、近年新しくなったという
「黒姫里之宮
黒姫山に
上之宮
中之宮
里之宮
の三体有り。
山宝水の湧き出る恵みを祀った祠です」
という碑がある。

里之宮
の三体有り。
山宝水の湧き出る恵みを祀った祠です」
という碑がある。

山頂に上之宮、雲龍寺に里之宮、そしてゴウロに中之宮、
水神である。
ということらしい。
ちなみに聞くところによると、
・黒姫弁財天の像は無い
・水害等で寺の場所は変わっている
とのことで、弁財天そのものは確認できない。
ということらしい。
ちなみに聞くところによると、
・黒姫弁財天の像は無い
・水害等で寺の場所は変わっている
とのことで、弁財天そのものは確認できない。
信濃町において「黒姫山を祀っているのは雲龍寺さん」というのは常識らしい。
黒姫山信仰、戸隠と妙高の間にある美しい山への信仰のあとをたどりたくなった。
次はゴウロへ。
黒姫伝説については、いずれ類型を整理したい。
2016/06/16
戸隠神社の年中行事として、6月の巳の日に行われる「種池祭」
ほどよい降雨があるよう行われる雨乞いです。
一般に公開されている行事ではありませんが、どうしても見たいと思い、休みを取って見学させていただきました。
戸隠神社は雨乞いの信仰を集めてきました。
ほどよい降雨があるよう行われる雨乞いです。
一般に公開されている行事ではありませんが、どうしても見たいと思い、休みを取って見学させていただきました。
戸隠神社は雨乞いの信仰を集めてきました。
種池のお水をいただき、神社の祈祷を受け持ち帰って田に注ぐと、雨が降るといい、いまでも各地から人々が雨乞いにこられるそうです。
戸隠スキー場でも12月1日は「雪乞祭」として、雪の中、種池(無雪期でも車道から歩いて15分ほどかかる)までお水を取りに行き、中社で祈祷を受けて、ゲレンデに蒔くという神事が行われています。
お水を運ぶ時は、「地面に置いてはいけない、降り返ってはいけない」という決まりがあり、白装束に身をつつんだ一行は、厳粛で美しいです。
(2015年12月の戸隠スキー場動画「雪乞祭」)
その雪乞祭の本家と言える「種池祭」
3か所で祝詞をあげるお祭が、粛々と執り行われました。
奥社入り口の「一龕龍王祠」
種池の主を祀ったものと言われています。鳥居をくぐってすぐのところにあります。

県道沿いの「念仏池」親鸞上人旧跡として知られています。
(2015年12月の戸隠スキー場動画「雪乞祭」)
その雪乞祭の本家と言える「種池祭」
3か所で祝詞をあげるお祭が、粛々と執り行われました。
奥社入り口の「一龕龍王祠」
種池の主を祀ったものと言われています。鳥居をくぐってすぐのところにあります。

県道沿いの「念仏池」親鸞上人旧跡として知られています。
この念仏池と種池が、この一帯において数少ない天然の池だそうです。
念仏池は、ぶくぶくと親鸞上人の念仏に湧く池。
澄み切った水の底から、いつも水が湧いています。

念仏池は、ぶくぶくと親鸞上人の念仏に湧く池。
澄み切った水の底から、いつも水が湧いています。

そして種池へ。登山道を15分ほど入ります。

『長野縣町村史 昭和11年』にも

『長野縣町村史 昭和11年』にも
「この池水は四面を全く陸地の囲みたる故、流出することなし。干魃の時、この池水を汲み持ち来りて祈れば、その里に必ず雨降るというをもって、これを種池という」とあります。

記録的な雪不足で山に蓄えられた雪が少なく、雨の降りかたも不安定な今年、適切な降雨がありますよう。

記録的な雪不足で山に蓄えられた雪が少なく、雨の降りかたも不安定な今年、適切な降雨がありますよう。