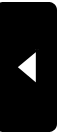2016/06/14
6月12日(日)、午後は栃原、解藁(ときわら)神社、春の例大祭へ。




時に振る舞いをいただきながら、20数戸の家々をゆっくり回ります。



解藁神社、という名の神社は唯一ではないでしょうか?
祭神は、天手力雄命、須佐之男命、大山祇命、金山彦命の四柱です。
『柵村史』には、「創立年月不詳、平の産土神。明治42年区内三社を合祀」とあります。
合祀されたのが、金比羅社と須賀神社で、その須賀神社の祀られているのが、このお神輿です。


栃原、平区町組におけるお祭。
須賀神社すなわち須佐之男命、例大祭は天王祭です。

先導の旗にも「奉納 素戔嗚尊」とあります。
豊作と無病息災を願うお祭なので、お神輿が田んぼから家々へと回ります。

お神輿は若衆により、各家へ、勢いよく走って入ります!
本格体力勝負なスタイル。

時に振る舞いをいただきながら、20数戸の家々をゆっくり回ります。

2時間あまりで、神社へ帰還。
最後もお神輿は走って行きました。


到着とともに花火が上げられ、ひと段落。

神前に奉告され、神楽の奉納をもってお祭の締めとなりました。




70年ほど前のお祭の写真が飾られていました。
雰囲気は変わらないながら、子供が多い…!


歴史の古さがうかがわれる立地と風情。
独特なあり方が守られている、貴重なお祭に立ち会いました。
2016/06/13
6月12日(日)、戸隠西条、尾倉沢古道の会による春の「砂鉢山登山会」が開催されました。
砂鉢山は、標高1,431.6m。
砂鉢山は、標高1,431.6m。
いくつも登山道があり、そのひとつが、田頭から入る尾倉沢古道です。
地元の皆さんが荒廃していた道を復活させ、草を刈るなど保全されています。







夜半の大雨に洗われた荒倉山系砂鉢山に、30名以上の参加者が市内外から集まりました。


林道から登山道を行きます。

登山道は、しっかりした道で、時折急なところもありつつ、歩きやすい道。
「古道」の名の通り、昭和の中ごろまで、鬼無里と柵を結ぶ最短の峠道だったそう。

古道の会の方によると、鬼無里のお祭に神主さんが行ったり、栃原、鬼無里など周囲の小学校の合同競技会が行われた際は、鬼無里から子供達がこの道を通ったそう。
往時は、裾花川沿いの道は狭隘で、わざわざ川まで降りて回り込むより、峠を越えたほうが早いというのは、歩いてみるとよくわかります。

鬼無里との境、地蔵峠に到着。

ひといき休憩に、民謡の披露が!
山中に、朗とした声が響きます。
小室節かな?山で聞くと格別です。
山頂まであと1時間!

というところで、一団と別れて下山。
午後は別件です。
徒歩や牛馬が移動の中心であった頃、この辺りの山々は、峠越えの道をたくさんのひとが往来していたのでしょう。
集落を結ぶ山道が無数にあり、その立地や合理性は、歩いてみると、さすがだなと思います。
里山の登山道は、多くがそうした古道をもとにしていますが、こうして地域のひとに守られて、歩くことができます。
少し昔に思いを馳せつつ、新緑を楽しみました。
花はフタリシズカがこれから咲いてきます。
2016/06/10
6月10日(金)、奥社を歩きます。
梅雨入りしても雨が少ないですが、今日はいっそうの晴天。
沢も水が少ないです。

ミヤマヨメナ、いっぱいになってきました。
写真は白いですが、実際は紫です。


群生するヤマサギゴケ。花の造形がかわいいです。


ヤマオダマキ。
奥社の社殿下にみられます。


ネコノメソウ、果実がついて猫の目っぽくなってきました。
若干ゾワゾワ系…


雨を受けやすいように、上向きのお皿の中に種ができるそうです。


戸隠牧場へ。
空が広くて気持ちが良いです。


今目立つのは、ミヤマキンポウゲの大群落。


花びらがツヤツヤしてます。


カロリー補給に、中社「らーめん徳さん」
飲み以外で来たのは初めて…!


海老ラーメン。
海老がプリプリ、塩ベースで野菜たっぷり。

ご飯ものもあります。餃子が美味しいです。
暑い日は冷やし担々麺かな。
2016/06/09
6月7日(火)、戸隠遭対協の登山道調査が行われました!
夏山シーズン前に、戸隠山、高妻・乙妻山、黒姫山、飯縄山西登山道〜瑪瑙山、戸隠西岳の登山道の安全確認等が実施されます。







戸隠山、蟻の塔渡りを越えて行くのは、「戸隠西岳」


登山マップに「熟練者向き、危険」の文字が多いバリエーションルート。
推定グレーディングE、体力レベル4〜5、ルート定数は34くらいでしょうか。
ガイドや経験者の同行無くては、踏みいる事のできない、戸隠の最深部です。
感想としては、「戸隠山+高妻山×鎖場マシマシ、危険度ハイレベル」でした。


雲の中を歩いて出会う、ハクサンイチゲの群生。
断崖絶壁の斜面に、白い可憐な花が満開!


例年よりも残雪がないため、春〜夏の花がいっせいに咲いています。


ミヤマクワガタやイカリソウ

たくさんの花で、忙しい稜線!
ですが、花に気をとられると、とっても危険です。

雲が晴れて、絶景が!
稜線上の道は、登り下りが果てしなく続きます。
岩壁の難所には、トラバース用のロープに助けられます。

そして核心部の西岳キレット、ほぼ垂直の長い鎖場。足場の狭さは筆舌に尽くしがたい。
かろうじて登って上から。

西岳山頂 2,030m。
稜線の眺めと花を楽しみつつ、まだまだ登ったり下ったり。
第一峰(P1)から、下りに入ります。

西岳の蟻の塔渡りからの眺め。
岩肌の緑が美しすぎるけど、高度感がハンパない。


この岩の背を渡り、数え切れないくらいの鎖場を、どんどんどんどん下ります。
鎖の間も、斜度はキツイ。


絶景の尾根道。鎖のトラバース。
足場は狭く、集中と緊張が続きます。
標高差900mほどをひたすら下ります。
鎖場が終わってホッとしても、林間は、堆積した落ち葉で滑りやすく気を抜けない。


採草地から振り返る。
あのギザギザに行ってしまったのだなあ。
約12キロ、10時間半の行程でした。
本当に、熟練者向け難関ルート。
読図能力と体力、ヘルメットと、クライミング技術が必須です。
奥社から八方睨、本院岳側から、P1尾根を降りるコースの方が、上りやすいそうです。
表山の蟻の塔渡りと、西岳キレットを「上りで通過できる」こと、P1尾根の急登と鎖場が体力と腕力を奪うこと、
長時間かかるので、体力や時間がなくなってから、表山を下りる危険が大きいこと、
などがあげられます。
バリエーションルートの難易度を体感しました。
2016/06/03
6月1日(水)、寒気が降りて、晴れていても涼しい戸隠です。
植物園は、バードウォッチャーの聖地です。

鳥の声が遠く近く響いてきます。

みどりが池ほとりのサラサドウダンの大きな木。
文字通り鈴なりの花。

ズダヤクシュの群生。
今はこの花が、いたるところにあります。

水辺のクリンソウ、咲いてきました。

サイハイランのつぼみ。咲くのが楽しみ。

増えてきました、ミヤマカラマツ。
雪のような花。

これはテンナンショウの仲間(コウライテンナンショウ?)ですが、

花が葉よりも低い、ヒロハテンナンショウ。茎は模様がないけど黒い。
同じ仲間なのに、近くにあるのに、明確に違うところがすごい。

午後の奥社。
夏の陽光になってきました。

参道脇に咲いてきたミヤマヨメナ。
たくさんつぼみがついているので、これから華やかになります!
中社「ゆたかや」さん。


歩いてお腹が空いたので、「ゆたか膳」
ざるそばに、そばコロッケ、おやきつき。

きりっとしたそばに、季節の小鉢がついて、大満足。
こちらは、そばコロッケをはじめ十割そば、ご飯物に「ジャンボ盛+1,000円!」など気になるメニューが多いです。

新緑の森の小道はいつまでも歩いていたい。